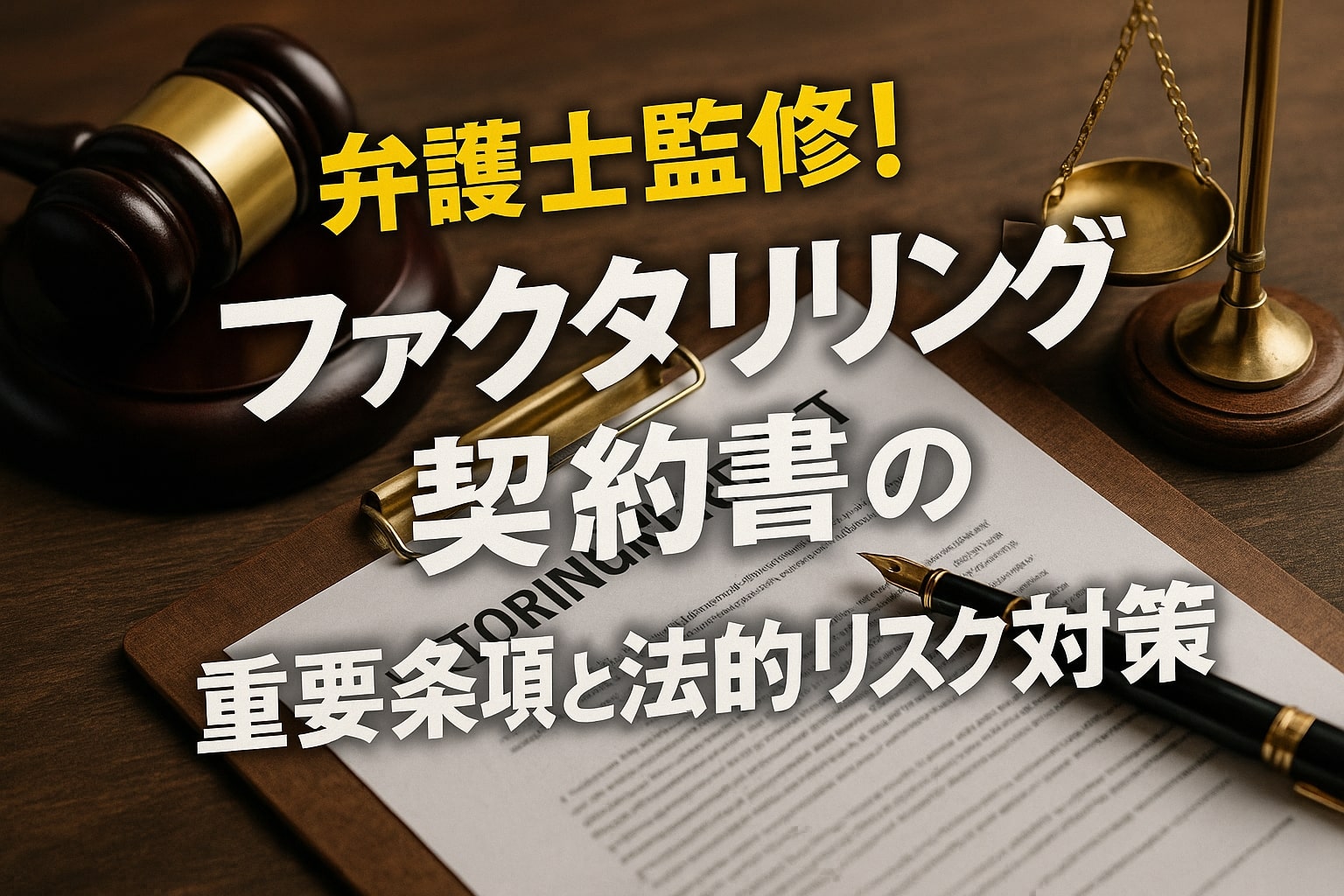「請求書を即キャッシュ化したいけど、ファクタリングって怖くない?」──そんなZ世代フリーランスのリアルな悩みに答えます!
私が法律系Webメディア編集者からフリーライターに転身した理由の一つが、「もっと身近に法律を伝えたい」という想いでした。
特に今、多くの若手クリエイターやフリーランスが直面している資金繰りの問題。
支払いサイトが長くて待てない、でも融資は審査が厳しい…そんなとき選択肢になるのがファクタリングです。
しかし、「怪しそう」「高い手数料を取られそう」といった不安を抱える方も多いはず。
本記事では、法律のプロである弁護士監修のもと、ファクタリング契約書に潜む重要ポイントと法的リスクを、私日向陽菜が解説します!
記事を読み終えると、以下のメリットが得られます。
- ファクタリングの基本的な仕組みがわかる
- 契約書のチェックリストで安全に利用できる
- 法的リスクの回避方法が具体的にわかる
- トラブル発生時の対応策がわかる
本記事では契約書の観点からファクタリングを解説しますが、業界全体の動向について理解を深めたい方は「ファクタリング賛否両論 | プロが業界の表と裏を見た実情」も参考になります。
それでは早速、ファクタリングの世界に飛び込んでみましょう!
ファクタリング超入門:ざっくり全体像
「ファクタリング」という言葉は知っていても、実際どんな仕組みなのか、融資との違いは何なのか、意外と理解していない方も多いのではないでしょうか。
まずは基本から押さえていきましょう!
ファクタリングとは?―貸付とどう違うの?
ファクタリングとは、企業や個人事業主が保有する売掛債権(まだ支払われていない請求書)を第三者に売却して、支払期日前に現金化する資金調達方法です。
法的には「債権譲渡契約」に分類される取引で、融資のような「借入」ではなく「売却」なんです。
この違いはとても重要!
融資の場合:
- お金を「借りる」ので負債になる
- 信用情報や財務状況の審査が厳しい
- 返済義務がある
ファクタリングの場合:
- 売掛債権を「売る」ので負債にならない
- 売掛先の支払能力が重視される
- 基本的に返済義務がない(ノンリコース型の場合)
ファクタリングは売掛債権を売却することで本来の入金予定日より前に現金化できる資金調達法で、融資などの借入れではないため金銭消費貸借契約を結ぶ必要はなく、法的には債権の売買契約に分類されます。
「え?でも高い手数料を取られるんでしょ?」という声が聞こえてきそうですね。
確かに手数料はかかりますが、それは「借金の利息」ではなく「債権を早く買い取ってもらうための割引料」という位置づけなんです。
取引の流れと登場人物(あなた・ファクター・取引先)
ファクタリングには大きく分けて「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」の2種類があります。
2社間ファクタリングの登場人物と流れ:
- あなた(債権者):売掛債権を持っている事業者
- ファクタリング会社(ファクター):債権を買い取る会社
流れとしては:
- あなたがファクタリング会社に売掛債権を売却
- ファクタリング会社から手数料を差し引いた金額が支払われる
- 支払期日にあなたが取引先から売掛金を回収
- あなたが回収した売掛金をファクタリング会社に支払う
ファクタリングの形態には、”2者間ファクタリング”と”3者間ファクタリング”があります。それぞれで契約の流れは異なります。
3社間ファクタリングの登場人物と流れ:
- あなた(債権者):売掛債権を持っている事業者
- ファクタリング会社(ファクター):債権を買い取る会社
- 取引先(債務者):あなたに代金を支払う予定の会社
流れとしては:
- あなたがファクタリング会社に売掛債権を売却
- ファクタリング会社から手数料を差し引いた金額が支払われる
- 取引先に債権譲渡の通知がされる
- 支払期日に取引先がファクタリング会社に直接支払う
2社間ファクタリングは、ファクタリング会社とファクタリング利用者の2者間で取引するファクタリングサービスで、売掛先の承認を得ずともファクタリング契約の締結ができるため、手続きが少なく取引がスムーズです。
それぞれにメリット・デメリットがあります。
2社間のメリットは、取引先に知られず迅速に手続きができること。デメリットは手数料が高めになることが多い点。
3社間のメリットは手数料が比較的低めなこと。デメリットは取引先に資金繰りを知られてしまうことです。
ファクタリングと債権譲渡の微妙な線引き
法的には「債権譲渡契約」に位置づけられるファクタリングですが、実際の取引の中身によっては「金銭消費貸借契約(融資)」と見なされるケースもあります。
この線引きがとても重要で、これが後ほど解説する「偽装ファクタリング」問題の根幹になります。
ファクタリングは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービスであり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。しかし、近時、ファクタリングを装った高金利の貸付けを行うヤミ金融業者の存在が確認されています。
ファクタリングと認められるための重要な要素:
- 売掛債権の未回収リスクをファクタリング会社が負っていること
- 手数料が担保目的とみなされるほど極端に高くないこと
- 債権の額面と関係のない金額での取引でないこと
これらの条件を満たさない場合、法的には「貸金業」と判断され、貸金業の登録がないファクタリング会社の場合は違法行為となる可能性があります。
裁判所は、当該契約がどれだけ金銭消費貸借契約に近づいているか、という点を大まかな視点として、判断しているものと思われます。
契約書チェックリスト:絶対に押さえたい主要条項
さて、ここからがこの記事の本題!
ファクタリング契約書を結ぶ際に、絶対に確認しておきたいポイントを解説します。
「契約書なんてめんどくさい…」という気持ちもわかりますが、後々のトラブルを避けるためにも必ずチェックしましょう。
譲渡対象債権の特定と範囲
まず確認すべきは、どの債権を譲渡するのかがはっきりと特定されているかどうかです。
通常、企業は複数の取引先に対する複数の債権を持っているものなので、どの取引先に対するどの債権を譲渡するのか、ファクタリング契約書で明示する必要があります。
チェックポイント:
- 取引先(債務者)の会社名が正確に記載されているか
- 対象となる請求書や契約書が特定されているか
- 債権額(金額)が明記されているか
- 債権の発生日と支払期日が明記されているか
特に、複数の請求書をまとめてファクタリングする場合は、すべての債権について上記情報が明記されているか確認することが重要です。
また、債権の一部のみを譲渡するケースは注意が必要です。
額面100万円の売掛債権のうち30万円のみ現金化するなど、売掛債権の一部買取はファクタリングに該当せず、融資と見なすとの裁判例もあります。
裁判例では、債権の一部だけを買い取るような取引は「偽装ファクタリング」(実質的には貸付)と判断されることがあるので要注意です。
リコース vs ノンリコース:責任の分岐点
ファクタリング契約における最重要条項の一つが「リコース(償還請求権)」に関する条項です。
ノンリコースとは:
売掛先が支払不能になった場合でも、ファクタリング利用者(あなた)は返済義務を負わない契約形態
リコースとは:
売掛先が支払不能になった場合、ファクタリング利用者(あなた)が責任を負う契約形態
償還請求権がある契約書は「リコース契約」といい、利用者は売掛先の倒産などによる貸し倒れのリスクも背負う形になります。対して、償還請求権がない契約書は「ノンリコース契約」といい、売掛先の倒産などによって売掛金が回収できなくても、利用者は責任を負う必要はありません。
本来、ファクタリングは「債権譲渡」ですから、譲渡後のリスクは買い手(ファクタリング会社)が負うのが原則です。そのため、ノンリコース型が「本来のファクタリング」と言えます。
リコース条項がある場合、実質的には「債権を担保にした融資」と判断される可能性が高くなります。
償還請求権があるファクタリング契約は悪質業者の常套手段でもあるため、避けたほうが無難でしょう。
契約書に「ノンリコース」であることが明記されているか、責任の所在について曖昧な表現がないか、しっかり確認しましょう。
手数料・遅延損害金・その他コスト
ファクタリングにかかるコストも重要なチェックポイントです。
手数料の割合により、ファクタリング契約のうまみが全く変わってくるので、契約書において、手数料が何%になっているのか、計算方法をしっかりチェックしましょう。
チェックポイント:
- 手数料の計算方法と金額が明記されているか
- 相場から大きく外れた手数料になっていないか
- 手数料以外の追加費用(事務手数料など)がないか
- 遅延損害金の計算方法と利率は適正か
手数料の相場は一般的に以下の通りです:
- 2社間ファクタリング:10〜15%程度
- 3社間ファクタリング:5〜10%程度
ただし、売掛先の信用度や支払いまでの期間によって変動します。極端に高い手数料(20%以上)の場合は要注意。これも「金銭消費貸借契約(融資)」と判断される要素の一つになります。
業者によっては高額の手数料を請求するところもあるため、契約前に手数料がいくらになるのか、よく確認することが大切です。
また、手数料の他に様々な追加費用を請求するケースもあります。特に悪質なのは「手数料+消費税」というケース。ファクタリングは非課税取引なので、消費税を請求するのは不適切です。
通知・承諾条項と債務者への影響
債権譲渡の通知方法についても確認が必要です。特に2社間ファクタリングの場合、売掛先への通知をどう扱うかが重要なポイントになります。
「債権譲渡通知」とは、売掛先である債務者に対して、債務者がファクタリング会社に代わったことを知らせる行為です。この債権譲渡通知の有無には、2者間ファクタリングのメリットが関係しています。
2社間ファクタリングでは、通常は売掛先に知られずに取引を行うことがメリットです。しかし、契約書によっては以下のような規定がある場合があります:
- 契約違反時に債権譲渡通知を行う条項
- 特定の条件下で債権譲渡登記を行う条項
2社間ファクタリングの契約にも、特約として債権譲渡通知が盛り込まれることがあります。例えば、利用会社が契約に違反する場合に、ファクタリング会社から売掛先へ債権譲渡通知書を送付する場合。
このような条項がある場合、どのような状況で通知が行われるのか、明確に理解しておく必要があります。売掛先に知られたくない場合は特に重要です。
契約解除・期限の利益喪失・準拠法
契約の終了や解除に関する条項も要チェック。特に注意したいのは以下の点です:
- 契約解除条件:どのような場合に契約が解除されるのか
- 期限の利益喪失条項:どのような場合に一括返済義務が生じるのか
- 準拠法と管轄裁判所:トラブル時にどこの法律が適用されるのか
契約書に記載のある義務を怠ると、損害賠償請求や違約金の支払いを求められることがあります。
特に注意したいのは、一方的にファクタリング会社に有利な解除条件や違約金条項です。たとえば「債権者の任意の判断で解除可能」といった曖昧な規定や、極端に高額な違約金の設定などは危険信号です。
また、準拠法と管轄裁判所が自分の所在地から遠い場合、トラブル発生時に不利になる可能性があります。
契約の確認に関する前項でも解説した通り、契約期間の確認も重要です。良心的でない業者の場合、利用に、数カ月~半年以上の継続利用を要求や、自動更新契約を求めてくるケースもあります。
契約期間や更新条件も必ず確認し、想定外の長期契約にならないよう注意しましょう。
見落としがちな地雷ポイントと法的リスク
契約書の主要条項をチェックするだけでなく、以下の法的リスクについても理解しておくことが重要です。特にこれから解説する「地雷ポイント」は、一見問題なさそうでも後々大きなトラブルになりかねない項目です。
二重譲渡・優先弁済リスク
同じ債権を複数のファクタリング会社に譲渡することを「二重譲渡」といいます。これは犯罪行為に該当し、絶対に避けるべきです。
「二重譲渡」とは、同じものを複数に渡り譲渡することです。売主が保有する1つの資産を、2人または複数の買主に別々に譲渡することであり、主に不動産業界で使われる用語といえます。
法的には、二重譲渡は以下の犯罪に該当する可能性があります:
- 詐欺罪(最大10年以下の懲役)
- 横領罪(最大5年以下の懲役)
1つの売掛債権を譲渡できるのは1社のみであり、二重譲渡は犯罪行為にあたります。そのため、資金調達の目的で同じ売掛債権を複数のファクタリング会社へ譲渡することは絶対に行わないようにしましょう。
二重譲渡がバレない、と考える方もいるかもしれませんが、以下の理由でほぼ間違いなく発覚します:
- 債権譲渡登記による発覚
- 支払期日に売掛金を両社に支払えないことによる発覚
- 内部告発による発覚
二重譲渡は「詐欺罪」と「横領罪」に問われます。資金調達を終えてから二重譲渡が判明すればこれらの罪に該当するのは当然ですが、見積り段階で判明しても罪に問われる可能性があるということです。
また、債権譲渡の対抗要件(第三者に権利を主張するための要件)として、債権譲渡登記がされている場合、先に登記した方が優先的に権利を主張できます。この点も理解しておくことが重要です。
偽装ファクタリング(貸金業法違反)の罠
「偽装ファクタリング」とは、表面上はファクタリング契約の形を取りながら、実質的には貸金業(金銭の貸付)を行っているケースを指します。これは貸金業法違反となる可能性があり、近年金融庁からも注意喚起がされている問題です。
金融庁は、「ファクタリングを装って、貸金業登録を受けていない者が、業として、貸付け(債権担保貸付け)を行っている事案が確認されています」と注意喚起しています。
偽装ファクタリングの特徴は以下の通りです:
- リコース条項(償還請求権)がある
- 極端に高い手数料を設定している
- 債権額と無関係の金額で取引している
- 実質的に売掛債権を担保にした融資の形態になっている
ファクタリング契約ないし債権譲渡契約において、譲受人に償還請求権や買戻請求権が付いている場合、債務者(売掛先等)への通知や債務者の承諾の必要がない場合や、譲渡人が譲受人から債権を回収する業務の委託を受け譲受人に支払う仕組みとなっている場合など、いま問題となっているファクタリング取引の多くは貸金業法および出資法の適用上、「金銭の貸付け」と解すべきです。
偽装ファクタリングに引っかかると、法外な金利で弁済額が膨らみ、厳しい取り立てを受ける恐れがあります。契約書の内容を精査し、上記の特徴に当てはまらないか確認することが重要です。
抗弁・相殺主張が飛んでくるケース
売掛債権が譲渡された後に、売掛先(債務者)から以下のような主張が出てくることがあります:
- 抗弁の接続:「商品・サービスに不備があったため支払いを拒否する」
- 相殺:「こちらも相手に対する債権があるので相殺する」
このようなケースは、特に3社間ファクタリングで問題になりやすいです。
この債権譲渡通知の有無には、2者間ファクタリングのメリットが関係しています。3者間ファクタリングでは、売掛金は債務者である売掛金から、新たに債務者となったファクタリング会社へ直接支払われます。
民法上、債権譲渡の通知前に債務者が債権者に対して持っていた抗弁事由は、譲受人に対しても主張できることになっています。つまり、商品やサービスに瑕疵があった場合、売掛先はファクタリング会社への支払いも拒否できる可能性があるのです。
このリスクを回避するためには:
- 品質の高い商品・サービスを提供する
- 取引先との関係を良好に保つ
- 売掛債権の内容について正確に開示する
といった対応が必要です。
個人情報・守秘義務違反とSNS晒しリスク
ファクタリング契約には個人情報や企業の機密情報が含まれていることが多いため、情報管理についても注意が必要です。
契約書には以下の点が明記されているか確認しましょう:
- 個人情報の取扱いについての規定
- 守秘義務(秘密保持)条項
- 情報漏洩時の責任の所在
中小企業経営にあたっては資金繰りや資金調達に際し、ファクタリングを利用される機会もあると思います。
また、トラブルが発生した際、悪質な業者がSNSなどで債務者を晒すような行為をすることもあります。そのような不当な行為に対する禁止条項があるかもチェックしておくと安心です。
消費者契約法・特商法が絡む意外な場面
個人事業主がファクタリングを利用する場合、以下の法律が適用される可能性があります:
- 消費者契約法:事業規模によっては「消費者」とみなされる場合がある
- 特定商取引法(特商法):訪問販売などの形態によっては適用される
通常、個人としてファクタリングを利用する機会はないと思いますが、「給与ファクタリング」という手法で、個人に貸付けを行うヤミ金融の存在も確認されていますので、こちらについても十分注意してください。
特に「給与ファクタリング」と呼ばれる個人向けファクタリングは違法性が高いとされています。個人の給与債権を担保にした貸付は、実質的には貸金業法違反のヤミ金融と判断される可能性が高いです。
個人事業主としてファクタリングを利用する場合も、事業用途であることを明確にし、消費者としての取引にならないよう注意しましょう。
弁護士が教える!リスク対策&トラブル防止策
ここまで、ファクタリング契約書の重要条項や法的リスクについて解説してきました。ここからは、実際にファクタリングを利用する際に役立つ具体的な対策法を紹介します。
条項ごとの”こう直せ!”修正文サンプル集
ファクタリング契約書の中で、特に注意が必要な条項と、その修正例を紹介します。
1. リコース条項(償還請求権)
危険な文言:
「債務者が支払わない場合、利用者は債権を買い戻さなければならない」
修正例:
「本契約はノンリコース型とし、債務者の不払いによるリスクはファクタリング会社が負担する」
2. 手数料条項
危険な文言:
「手数料は○○円とするが、ファクタリング会社の判断で変更できる」
修正例:
「手数料は○○円(債権額の○○%)とし、契約締結後の変更は双方の合意がない限り行わない」
3. 契約解除条項
危険な文言:
「ファクタリング会社は任意のタイミングで本契約を解除できる」
修正例:
「契約解除は、相手方が重大な契約違反を行った場合のみ可能とする」
後々トラブルに遭ったり、不利益を被ったりしないよう、契約書に署名した後でも、任意のタイミングで契約解除できるかも確認しておきましょう。
4. 通知条項
危険な文言:
「ファクタリング会社は任意のタイミングで債務者に債権譲渡通知を行うことができる」
修正例:
「債権譲渡通知は、利用者が本契約に違反し、書面による是正要求から30日以内に改善がない場合のみ行うことができる」
契約書の文言に不安がある場合は、契約前に弁護士に相談するか、ファクタリング会社に説明を求め、納得できない場合は修正を依頼しましょう。
デューデリジェンスで見るべき3つの証憑
ファクタリング会社を選ぶ際には、相手の信頼性を確認するデューデリジェンス(調査)が重要です。確認すべき主なポイントは以下の通りです:
1. 会社の基本情報
- 会社の実在性(登記事項証明書、事業所の実在確認)
- 設立年数(長期運営は信頼性の証)
- 貸金業登録の有無(登録があれば監督下にある証拠)
2. 評判・口コミ
- インターネット上の評判
- 業界団体への加盟状況
- 過去の訴訟歴
3. 契約関連資料
- 契約書のひな形
- 手数料の明示
- 説明の丁寧さと透明性
欧米では企業を買収したり不動産を購入したりする際に、購入者側の負担で対象の企業や物件の状態の調査、つまりデューデリジェンスを実施することが一般的です。デューデリジェンスを行う理由としては、売却側から提示された情報のみで判断するのは、客観性や信頼性に欠けるためです。
相手に関する情報を入念に調査することで、悪質な業者を避けることができます。「急いでいるから」と調査を怠らないようにしましょう。
電子契約・クラウドサイン運用Tips
最近では電子契約サービスを利用したファクタリング契約も増えています。特に「クラウドサイン」などの電子契約サービスを活用する場合のポイントを紹介します。
専用フォームから申し込めば、仮審査や見積もりが行われたのち、Web上で必要書類を提出し、クラウドサインなどを利用した電子契約という流れになるため、一連の作業がオンライン上で完結できます。
電子契約のメリット:
- 印紙税の節約(電子契約には印紙税がかからない)
- 契約締結の迅速化
- 保管・管理の容易さ
ただし、電子契約の場合も契約内容の確認は怠らないようにしましょう。画面上でスクロールするだけで確認せず、必ずダウンロードして内容を精査することをおすすめします。
電子契約にて『クラウドサイン』を活用することで、申込書、通帳、請求書、身分証明書など必要書類の提出がスムーズになりすぐに審査に取り掛かれ、契約完了が早まれば素早く資金の振り込みが出来ます。
また、電子契約の履歴や証明力を確保するため、以下の点に注意しましょう:
- 契約締結の証拠として電子署名の記録を保存する
- 契約書のPDFをダウンロードして保管する
- メールのやり取りなど、交渉過程の記録も残しておく
もし揉めたら?交渉→訴訟のフローチャート
万が一、ファクタリング会社とトラブルになった場合の対処法です。
Step 1: 問題の整理と証拠収集
- どのような問題が発生したか明確にする
- 契約書、メールのやり取り、振込記録など証拠を収集
- 内容証明郵便などのやり取りも保存
Step 2: 直接交渉
- まずは当事者同士での話し合いを試みる
- 可能であれば書面で交渉内容を記録
- 無理な要求はせず、現実的な解決策を模索
Step 3: 弁護士・専門家への相談
- 直接交渉で解決しない場合は法律の専門家に相談
- 弁護士に依頼して内容証明郵便などを送付
- 法的なアドバイスをもとに次のステップを検討
ファクタリングの裁判例には、ファクタリング会社が原告となって訴えたものと、訴えられて被告となったものがあります。ファクタリング会社が原告となるのは、利用会社が約束通りにファクタリング会社へ回収した売掛金を入金しないため、回収のために訴えるパターンです。
Step 4: ADR(裁判外紛争解決手続き)の利用
- 裁判よりも費用と時間を抑えられる可能性
- 中立的な第三者のもとで和解を目指す
- 金融ADRなどの専門機関の利用も検討
Step 5: 訴訟提起
- それでも解決しない場合は訴訟を検討
- 訴訟には相応の費用と時間がかかることを理解
- 弁護士と相談し、勝訴の見込みを検討
「ファクタリングを利用したならお金を取り戻せる可能性があるので、訴訟を起こすと良い」とアドバイスを行い、原告代理人弁護士を紹介しているようです。こういった事情を背景に、本来なら認められないようなファクタリング会社相手の訴訟が近年数多く発生しているのではないかと思われます。
最近では「ファクタリングは違法だから返金されるはず」と安易に訴訟を勧める例もありますが、実際には契約内容や条件によって結果は大きく異なります。「ノンリコース型」の通常のファクタリング契約であれば、訴訟を起こしても請求が棄却されるケースが多いです。
不当な訴訟は弁護士費用や時間の無駄になるので、専門家のアドバイスをもとに慎重に判断することが重要です。
まとめ
この記事では、ファクタリング契約における重要条項と法的リスク、その対策について詳しく解説してきました。ここまでの内容をまとめると:
1. 重要条項のチェックポイント
- 譲渡対象債権の特定と範囲
- リコースvsノンリコース(償還請求権の有無)
- 手数料・遅延損害金・その他コスト
- 通知・承諾条項と債務者への影響
- 契約解除・期限の利益喪失・準拠法
売掛債権譲渡契約書は条項の数が多く複雑です。複雑だからと面倒がらずにしっかり契約書に目を通し、よくわからない条項や疑問を感じる部分は、納得できるまで説明してもらうことが大切です。
2. 要注意の法的リスク
- 二重譲渡・優先弁済リスク
- 偽装ファクタリング(貸金業法違反)の罠
- 抗弁・相殺主張が飛んでくるケース
- 個人情報・守秘義務違反とSNS晒しリスク
- 消費者契約法・特商法が絡む意外な場面
3. トラブル防止のための対策
- 条項ごとの修正文例の活用
- デューデリジェンスの実施
- 電子契約・クラウドサインの活用
- トラブル発生時の対応フローの理解
上記の特徴に合致するファクタリング業者は、違法な偽装ファクタリングの可能性が高いので注意しましょう。ファクタリングを利用するときには契約内容を慎重に確認し、不明な点があるなら質問して明らかにしてください。
ファクタリングは、使い方を間違えなければ非常に有用な資金調達方法です。契約内容をしっかり理解し、法的リスクを把握した上で利用することで、安全かつ効果的に活用できます。
「疑わしきは条文チェック+弁護士相談」が最強メソッド。わからないことがあればプロに相談し、納得した上で契約を結ぶようにしましょう。
そして最後に、本記事で紹介した契約書レビューのポイントを、明日からのファクタリング利用に役立ててください。適切な知識でキャッシュフローを守り、ビジネスを成長させましょう!