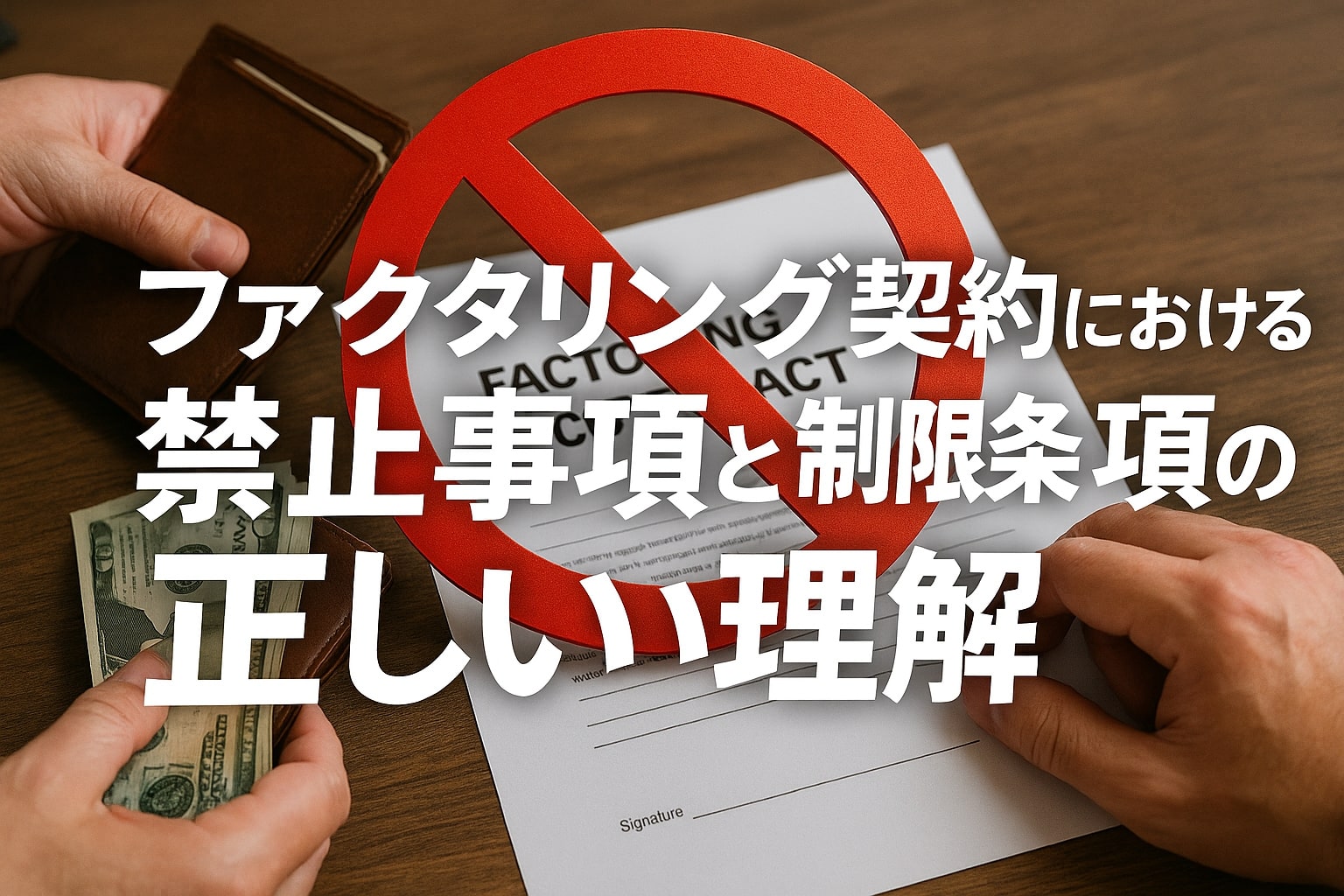「ファクタリング」って言葉、最近よく耳にするけど実際どんな契約なの?
私がTikTokで解説動画を上げたら、「そういえば友達がファクタリングで資金調達してた」という反応が結構あったんです!
実は、フリーランスやインフルエンサーの間でも少しずつ認知されてきているこの資金調達方法。
でも、どんな取引にも「やっちゃいけないこと」や「気をつけるべきこと」があります。
今回は、法律のお姉さん・陽菜が、ファクタリング契約で特に注意したい禁止事項と制限条項について、わかりやすく解説していきます。
目次
ファクタリング契約の基本をおさらい
ファクタリングとは?ざっくり3行で説明!
ファクタリングとは、企業や個人事業主が持っている「売掛金(まだ支払われていないお金)」を早めに現金化するサービスです。
簡単に言うと、「来月入る予定の100万円の売掛金を、手数料を引いた90万円で今すぐ受け取る」という取引。
法律的には「債権譲渡契約」に分類され、借金ではなく「売掛債権の売却」になるのがポイントです。
どういう人・企業が利用するの?
ファクタリングを利用するのは、主に以下のような方々です:
- 1. 資金繰りに悩む中小企業
- 2. 大口案件の支払いまで資金が必要なフリーランス
- 3. 急な設備投資が必要になった個人事業主
- 4. 売掛金の回収リスクを減らしたい企業
特に最近は、フリーランスやインフルエンサーなど、個人で活動する方々にも浸透してきています。
SNSで注目を集めているけれど、実際の案件の入金は数ヶ月先…というときに、資金調達手段として活用されることも。
ファクタリングとローンの違い
「結局、お金を先に受け取るんだから、借金と同じでしょ?」と思った方!
実はファクタリングとローンは根本的に異なるものなんです。
ローンは「借入」でバランスシート上の負債になるけど、ファクタリングは「売却」なので資産と現金が入れ替わるだけ。信用情報にも影響しません。
ファクタリングは契約形態によって「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」に分かれます。
2者間は売掛先に知られずに取引できる一方、3者間は手数料が安くなる傾向があります。
どちらを選ぶかは、自分のビジネス状況によって判断しましょう。
禁止事項って何を指すの?
よくある禁止条項リスト(例:二重譲渡、債権の性質制限など)
ファクタリング契約では、契約書に「禁止事項」として明記されていることがいくつかあります。
最も重要な禁止事項は以下の3つ。絶対に守らなければなりません:
- 1. 売掛債権の二重譲渡
- 2. 架空請求や虚偽の債権譲渡
- 3. 契約で禁止されている債権の譲渡
特に「二重譲渡」は絶対NGな行為。
同じ売掛債権を複数のファクタリング会社に売却することは、法律違反になる上に必ず発覚します。
「売掛先が誰にも言わなければバレないのでは?」と考える人もいるかもしれませんが、それは大きな間違い。
なぜ禁止されるの?法律的な背景を簡単に
二重譲渡が禁止される理由は、それが詐欺罪や横領罪に該当する犯罪行為だからです。
ファクタリングでは、売掛債権という「権利」を売買するため、物理的には同じ債権を複数回譲渡することも可能です。
でも、それは「すでに自分のものではないもの」を売ることになり、民法上も刑法上も問題があります。
債権譲渡の登記制度や、最終的に売掛金の支払期日が来たときの支払先の問題など、様々な場面で二重譲渡は発覚します。
法律の世界では「対抗要件」という言葉がありますが、これは簡単に言うと「誰が本当の権利者か」を決めるルールのこと。債権譲渡登記をした方が強い立場になります。
「知らなかった!」では済まされないトラブル事例
ある中小企業のAさんは、資金繰りに困って同じ売掛債権を2つのファクタリング会社に譲渡してしまいました。
「どうせバレないだろう」と思っていましたが、支払期日が来た時に一方のファクタリング会社が入金確認できず調査を開始。
結果、二重譲渡が発覚して法的措置を取られただけでなく、取引先からの信用も失ってしまいました。
実は、二重譲渡はこんな形で必ずバレます:
- 債権譲渡登記での発覚(先に登記した会社が優先される)
- 支払期日に資金が足りず発覚
- 内部告発や関係者からの通報
「資金繰りに困って」という理由があっても、二重譲渡は犯罪行為。
最悪の場合、詐欺罪で10年以下の懲役という厳しい結果になることも理解しておきましょう。
制限条項ってどういう意味?
禁止とは違う「制限」ってどこがポイント?
ファクタリング契約には「禁止事項」だけでなく「制限事項」も存在します。
禁止は「絶対にやってはいけないこと」、制限は「条件付きでしか認められないこと」と理解すると分かりやすいですね。
主な制限条項には以下のようなものがあります:
- 1. 債権の一部譲渡の制限(全額でないと譲渡できない)
- 2. 譲渡可能な債権の種類の制限(特定の取引先のみOKなど)
- 3. 支払期日までの制限(あまりに遠い将来の債権は不可など)
これらの制限は、ファクタリング会社がリスク管理するために設けているものです。
つまり、会社によって「この債権は買い取れる」「この債権は買い取れない」という基準が異なります。
契約前に、自分の持つ売掛債権が相手の基準に合っているか確認しておくことが大切です。
実際の契約書に出てくる文言の例と解説
実際の契約書ではどんな風に制限条項が書かれているのでしょうか?
以下は、よく見られる制限条項の文言例です:
「甲(利用者)は、対象債権の全部または一部について、乙(ファクタリング会社)以外の第三者に対して譲渡、担保提供その他の処分を行ってはならない」
これは、ファクタリング会社に譲渡した債権を他者に譲渡できない、という当然の制限です。
「譲渡対象債権は、甲と丙(売掛先)の通常の商取引によって生じた債権に限るものとする」
この条項は、通常の商取引以外(たとえば個人的な貸し借りなど)で発生した債権は譲渡できない、という意味です。
制限条項はファクタリング会社によって異なりますが、基本的には「リスクの高い債権」を排除するためのものと理解しておきましょう。
制限を破ったらどうなる?ペナルティと信用の問題
制限条項に違反した場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか?
契約書には、違反時の罰則として以下のような内容が含まれていることが多いです:
- 1. 契約解除(直ちに契約が終了する)
- 2. 損害賠償(会社が被った損害を支払う)
- 3. 違約金の支払い(契約で定められた金額)
- 4. 受け取った資金の即時返還
特に深刻なのは、信用を失うというペナルティです。
一度制限条項に違反すると、そのファクタリング会社との取引が難しくなるだけでなく、業界内での評判も落としかねません。
ファクタリング会社は自社の顧客情報を他社と共有することもあり、一社での問題が他社利用にも影響することがあるのです。
フリーランスや個人事業主が気をつけたいこと
フリーで受けた仕事の債権、ファクタリングに出してもいいの?
「フリーランスや個人事業主もファクタリングを利用できるの?」という質問をよく受けます。
結論から言うと、利用できます!むしろ最近は個人向けのファクタリングサービスも増えています。
ただし、以下の点に注意が必要です:
フリーランスがファクタリングを利用する際のチェックポイント:
- 1. 業務委託契約書があるか(口約束だけだと審査が通りにくい)
- 2. 請求書が発行できるか(ファクタリングには必須)
- 3. 継続的な取引実績があるか(一時的な取引だと審査が厳しい)
特に「業務委託契約書」の存在は重要で、2024年11月から施行されたフリーランス保護新法でも契約書作成が義務化されています。
口約束での仕事が多いフリーランスの方は、今後のためにも必ず契約書を交わす習慣をつけましょう。
契約書チェックの3ステップ:ここだけは見逃さないで!
ファクタリング契約書をチェックする際、特に以下の3ステップは必ず確認してください:
ステップ1:償還請求権の有無を確認する
償還請求権とは、売掛先が支払わなかった場合に、あなたに返済を求める権利のこと。
通常のファクタリングでは「ノンリコース(償還請求権なし)」が一般的です。
もし契約書に「買戻し条項」「補償義務」などの言葉があれば、それは償還請求権がある可能性があります。
ステップ2:手数料の内訳を確認する
ファクタリング手数料には以下のような費用が含まれていることがあります:
- 基本手数料
- 審査料
- 振込手数料
- 事務手数料
パーセンテージだけでなく、具体的な金額もしっかり確認しましょう。
ステップ3:契約解除条件を理解する
どのような場合に契約が解除されるのか、その場合にどのようなペナルティがあるのかを確認します。
特に「債務不履行」の定義や「損害賠償額」については、あいまいな表現がないか注意深くチェックしてください。
相談すべき?弁護士or専門家の使いどき
「契約書の内容がよくわからない…」というのは、多くのフリーランスや個人事業主が感じる不安です。
そんなときは、以下のような専門家に相談することを検討しましょう:
- 1. 弁護士(契約内容の法的リスクを評価してくれる)
- 2. 税理士(税務上の影響を確認できる)
- 3. 中小企業診断士(経営面からのアドバイスがもらえる)
特に初めてファクタリングを利用する場合や、高額な取引を行う場合は、専門家のチェックを受けることをおすすめします。
「少し相談料を払うのはもったいない」と思うかもしれませんが、後からトラブルになって大きな損失を被るリスクと比べれば、予防的な相談費用は安い投資と言えます。
また、フリーランス向けの無料相談窓口も活用できます。「フリーランス・トラブル110番」などの公的な相談窓口もあります。
トラブルを防ぐ!契約前にやっておくべきチェックリスト
チェック① 相手先の信頼性
ファクタリング会社の信頼性を確認するためのチェックリスト:
- 1. 会社の実在性(登記情報、住所、連絡先の確認)
- 2. 会社の評判(口コミ、レビュー、SNSでの評価)
- 3. 運営年数(長く事業を続けているか)
- 4. 公式サイトの内容(透明性のある料金体系か)
特に注意すべきは、あまりにも好条件を謳う会社や、前払い金を要求する会社です。
「業界最安手数料」と言いながら、あとから追加料金を請求するケースもあるので気をつけましょう。
チェック② 契約条項の読み込み方
契約書の読み方のコツは以下の通りです:
- 1. 定義条項から読む(契約書内の重要な言葉の定義を確認)
- 2. 重要な数字に印をつける(手数料率、支払期限など)
- 3. 「しなければならない」「してはならない」という表現に注目
専門用語が多くて難しければ、噛み砕いた言葉で書き直してみるのも良い方法です。
私自身、弁護士ではないけれど法学部出身として、契約書は「自分の言葉に置き換える」ことで理解を深めています。
チェック③ 自分に不利な文言がないか
特に以下のような条項には注意が必要です:
- 1. 一方的な契約解除権(ファクタリング会社だけが解除できる)
- 2. 過剰な違約金(債権額を超える違約金の設定)
- 3. 管轄裁判所(遠方の裁判所が指定されていないか)
- 4. 秘密保持義務の範囲(あまりに広すぎないか)
こうした不利な条件があれば、交渉できる可能性もあります。
特に大手のファクタリング会社は、ある程度の条件交渉に応じてくれることもあるので、納得がいかない点は遠慮なく質問しましょう。
チェック④ ググるだけじゃ足りない!公的情報の探し方
ファクタリングに関する情報は、一般的な検索エンジンだけでなく、以下のような公的な情報源も活用しましょう:
- 1. 金融庁のウェブサイト(ファクタリングに関する注意喚起)
- 2. 国民生活センターの相談事例(トラブル事例の把握)
- 3. 公正取引委員会の報告書(違法な事例の確認)
- 4. 地方自治体の消費生活センター情報(地域のトラブル事例)
特に金融庁は「ファクタリングの利用に関する注意喚起」を出しており、偽装ファクタリングの見分け方などが解説されています。
また、判例データベースなどを活用すれば、過去のファクタリングに関する裁判例も確認できます。
よくある質問と回答
Q1: ファクタリングで二重譲渡したことがバレるのはなぜ?
A1: 債権譲渡登記制度によって債権の譲渡履歴が公的に記録されることや、支払期日の際に同じ債権に対して複数の権利者が現れることで必ず発覚します。
二重譲渡は詐欺罪や横領罪といった犯罪行為ですので、絶対に行わないでください。
Q2: 償還請求権がある契約は避けるべきですか?
A2: 基本的には「ノンリコース(償還請求権なし)」の契約を選ぶべきです。
償還請求権があると、売掛先が支払わない場合にあなたが返済する義務を負うことになり、実質的には融資と変わらなくなってしまいます。
Q3: フリーランスがファクタリングを利用する際の審査は厳しいですか?
A3: 企業に比べると審査はやや厳しめですが、業務委託契約書や過去の取引実績があれば十分利用可能です。
最近は個人事業主やフリーランス向けのファクタリングサービスも増えているので、複数社を比較検討してみるとよいでしょう。
まとめ
- ファクタリング契約における「禁止事項」と「制限条項」の違いを理解することが大切
- 二重譲渡は犯罪行為であり、必ず発覚するので絶対に行ってはいけない
- 契約書はしっかりチェックし、特に償還請求権の有無や手数料の内訳を確認する
- フリーランスや個人事業主も利用できるが、業務委託契約書など必要書類を準備しておく
- 不安な点は専門家に相談し、公的情報も活用して安全に利用することが重要
「法律のお姉さん」からの最後のアドバイス:契約は”読んで、疑って、守る”が基本!
ファクタリングは上手く活用すれば、フリーランスや個人事業主の強い味方になります。
でも「お金がすぐに手に入る」という魅力に惑わされて、契約内容をしっかり確認せずに利用すると痛い目を見ることも。
知識武装して、賢く安全にファクタリングを活用していきましょう!